「自己分析をちゃんとやったはずなのに、ESが通らない」「過去を振り返って自分の強みはわかったけどけど、どの企業が合うのか全然わからない」
そんな悩みはありませんか?
実は私も大学3年の秋頃、まさに同じ状況でした。過去の自分史を書いて、長所・短所を整理して、「これで準備万端!」と思ったのに、いざ企業選びになると全く進まない。友達は「やりたいことが見つかった」と言っているのに、自分だけ取り残された気分になっていました。
でも、ある時気づきました。
私がやっていたのは「自己分析」ではなく、単なる「過去の整理」だったということ。多くの学生が陥りがちな自己分析の失敗パターンとして、「やりたいこと探し」に偏ってしまうケースがありますが、私もその一人でした。
実際に就活を経験して企業選びに成功した今だからこそわかる。
「企業選びに直結する自己分析」の本質的なやり方があります。
この記事では、
「なぜ自己分析がうまくいかないのか」「どこを修正すれば企業選びにつながるのか」を具体的に解説していきます。過去の振り返りではなく「価値観の言語化」に重点を置いた分析方法や、企業情報との照らし合わせ方まで、ステップごとにお伝えします。
読み終わる頃には、今のモヤモヤした状況から抜け出して、「この企業なら自分の価値観と合いそう」と確信を持って志望企業を選べるようになるでしょう。
なぜ自己分析がうまくいかないのか?企業選びで失敗する3つの「やり方のズレ」
自己分析をやったはずなのに、なぜか志望企業が決まらない、ESで志望動機が書けない…。そんなモヤモヤを抱えているあなた、実はとても多いんです。
実はこれ、自己分析の「企業選びへの活かし方」にズレがあることが原因なんです。理系学生が企業選びで迷子になる3つのパターンを見ていきましょう。
パターン1:「好きなこと」だけで業界・企業を選んでいる
「化学が好きだから化学メーカー」「ITに興味があるからIT企業」「街歩きが好きだから不動産業界」
一見合理的に見えますが、「好き」と「向いている」は全然違います。私の先輩で、食品が好きだからメーカーに入ったけれど、実際入社後は工場の管理の担当になり、やりたいことと違ったとおっしゃっていました。
パターン2:「企業研究」と「自己分析」を別々にやっている
自己分析で「協調性がある」と分かったのに、企業選びでは「年収」「知名度」だけで判断。これでは面接で「なぜうち?」にという質問にも答えられませんし、入社後ギャップが生まれてしまう可能性も高いです。
パターン3:「完璧な企業」を探してしまっている
企業選びにおいて「最適解」を求めがちですが、すべての条件を満たす企業なんて存在しません。
私は最後までどの企業が自分にとって一番いいのか答えが出るまで探し続けていましたが、結局はどの企業も素晴らしい点、懸念点がそれぞれ存在します。
懸念点をどれだけ妥協できるか、懸念点はありつつも自分にとって良い点がどのくらいの大きさなのか。これを考える必要が最終的には出てきます。
それを念頭において就活しなければ、答えのないものに正解を求めるという非常に苦しい戦いになってきます。
次のセクションでは、これらのズレを修正して、自分にぴったりの企業を見つける具体的な方法をお伝えしますね。
論理的にわかる!企業選びに活かせる自己分析の正しいステップ
さて、前のセクションで「やり方のズレ」が分かったところで、今度は正しいアプローチを見ていきましょう。理系学生らしく、論理的に進められる2ステップをご紹介します。
ステップ1:具体的に自分の過去を洗い出す
まずはデータ収集から。過去の経験を時系列で書き出していきます。
洗い出すべき項目:
- 小学校〜大学までの印象深い出来事
- 部活・サークル・アルバイトでの経験
- 今までの成功体験・失敗体験
- 人間関係で嬉しかった/辛かった出来事
私の場合、「高校の体育祭でリーダーをやった」「習い事で結果が出ずに挫折した」「サークルの企画を任されて成功させることができた」などの経験を思い出しました。
この段階では質より量。とにかく思い出せる自分にとっての人生の分岐点や特に記憶に残る出来事ことを書き出すのがコツです。
他人から見た自分はどのような人物か聞いてみるのもおすすめです!
自分では意外と気づかなかった強みや価値観にであえるかもしれませmんよ!
ステップ2:過去の体験を深堀する
次に、ステップ1で集めたデータを分析します。
「なぜそれが印象に残っているのか?」「そこから何が見えるのか?」を考えます。
深堀方法: 各エピソードに対して「なぜ?」を3回繰り返す。例えば私の体育祭のリーダー経験なら:
- なぜ印象に残った?→みんなで目標達成した瞬間の達成感が味わえたから
- なぜみんなで達成できた?→チームの目標設定を明確にしたから
- なぜそうした?→チーム全体で一つの目標に向かうことで一体感が生まれると思ったから
ここから「チームワークを重視する価値観」が見えてきます。
言語化することで「自分はこういうことを大事にしていたのか!」と改めて理解することができます。
ステップ3:抽象化したものに当てはまる企業は何か探す
ステップ2を深堀ってみると、気づくことがあるはずです。
同じような価値観で達成感ややりがいを感じていることに。
その価値観が見えてきたらその具体→抽象化へ
そしてその抽象化したものをグループ化しましょう!
例えばこんな感じ。
・チームで何かを成し遂げたときに自分のやりがいを感じる
・周りの熱量が高いと自分の熱量が上がる
・プレイヤーとして目標を追っているときが一番楽しかった
・落ち着いていて自分のペースで淡々と物事をこなしている方が結果が出た
このように今までの過去の経験から自分の価値観を抽象化します。
ここで初めて、
それではどこの企業の価値観が自分の価値観とあっているのかな?
と照らし合わせることができるのです。
ステップ4:自分の価値観と企業の価値観を照らし合わせる
ステップ2で見えた価値観や強みを使って、実際に企業を絞り込みます。ここが一番重要なポイント。
具体的なやり方: 抽象化で見えた要素を企業選びの「軸」にする。例えば「チームワークを重視する」なら:
- 企業HPで「チーム制」「協働」というキーワードを探す
- 面接で「チームでの取り組み」について質問してみる
- OB/OG訪問で職場の雰囲気を確認する
私は「チーム力を発揮できる団体で自分がリーダーを務めているときにやりがいを感じていた」ので「仕事内容は個人的な成果だけを追っていないか」「先輩や後輩の距離感はどのくらいか」などを中心に見ていきました。
結果的に最高の職場に出会えたと思っています。
注意ポイント: 完璧にマッチする企業はありません。7割程度合っていれば十分です。
自己分析から企業選びの軸を作る方法
前のセクションで過去の体験を洗い出して抽象化できたら、今度はそれを企業選びの軸に変換していきます!
「価値観」を「企業選びの条件」に変換する
抽象化で見えた価値観を、企業選びの判断基準にします。
例えば「自己成長をする」価値観(自己成長にも様々な定義がありますが!):
- 研修制度が成長の観点で充実している企業
- 若手にも責任ある仕事を任せる企業
- 定期的なフィードバックがある企業
私の場合「チーム全体で成果を出したい」という価値観だったので、個人成績よりチーム評価を重視する企業を中心に見ました。
「強み」を「企業選びの条件」に変換する
次に、強みを活かせる職場環境を考えます。
「継続的な改善が得意」なら品質管理や業務効率化を重視する企業、「新しいアイデアを出すのが得意」なら新規事業や企画職がある企業、といった具合です。
「自分が外せない制度」を「企業選びの条件」に変換する
過去の価値観や強みとは少し離れますが、「制度条件軸」(給与・勤務地など)の条件を軸にも組み込みましょう。私は具体的に「東京勤務」「基本給28万以上」という条件で企業を絞っていました。
お金がないとどれだけいい企業でも生活するのに苦労すると考えていました!
生活水準も考えたうえで条件を絞ってみてください。
実例:価値観別に見る向いている企業タイプ
自己分析で価値観が見えてきたら、それがどんな企業タイプとマッチするかを知っておきましょう。以下の表を参考にしてください。
あくまで例です!‼自分の目で見て確かめて価値観と照らし合わせてみてください。
| 価値観 | 向いている企業の特徴例 |
|---|---|
| 裁量・成長 | ベンチャー企業/ITスタートアップ/外資系 |
| 安定・人間関係 | インフラ系企業/地方自治体/大手メーカー |
| 社会的意義 | 教育/医療/NPO/行政と連携する事業 |
| 論理・専門性 | コンサル/研究職/開発系企業 |
実際の活用例
私の大学の先輩は「裁量・成長」タイプで、創業3年のスタートアップに入社しました。「大企業だと承認プロセスが長すぎて、自分のアイデアがすぐ試せない」と言って転職を決めたそうです。
一方、同期の友人は「安定・人間関係」重視で大手メーカーを選択。「長期的なプロジェクトで腰を据えて取り組みたい」という価値観にぴったりマッチしています。
重要な注意点: 実際には「組織の中身」を知る努力が必要。同じ業界でも企業によって文化は全然違いますからね。
中身を知るためには説明会やOB訪問で話を聞くのは必須です!
OB訪問のことなら過去に解説したブログも参考にしてください!
→OBOGがいない大学生のためのOB訪問|”不利”を乗り越える2つの実践法
OB訪問でおすすめのアプリ
自己分析を”企業選びの武器”にするための注意点
自己分析の方法が分かったところで、実際に企業選びで活用する際の注意点をお伝えします。ここを間違えると、せっかくの分析が無駄になってしまいます。
「やりたいこと探し」に偏ると危険
多くの学生が「やりたいこと=職種」だけにフォーカスしがちですが、これは業界選びを見誤る原因になります。
例えば「マーケティングがやりたい」と思っても、BtoB企業とBtoC企業、スタートアップと大企業では、同じマーケティングでも働き方が全く違います。職種より「どう働きたいか」「どんな価値観に共感するか」の方が本質的です。
私も最初は「企画をやりたい」だけで企業を選んでいましたが、実際に重要だったのは「チームで課題解決する環境」でした。
オススメ:企業比較ノートを作って分析視点を定着させる
感情で企業を選ばず、「なぜこの企業に惹かれるのか?」を言語化する習慣をつけましょう。
企業比較ノートの項目例:
- 価値観との一致度(5段階評価)
- 社員の雰囲気(説明会やOB訪問での印象)
- 評価制度(成果主義 or 年功序列)
- 社風(個人主義 or チーム重視)
このノートを作ることで、「なんとなく良さそう」から「論理的に合っている」という判断に変わります。面接でも「なぜうちの会社?」に説得力を持って答えられるようになりますよ。
「ノート作るのめんどくさい…」と思った方、最初は3社だけでも大丈夫です。比較する癖をつけることが大切です。
まとめ|企業選びで迷うなら、”自己分析の精度”を見直そう
自己分析をちゃんとやったのに企業選びで迷うのは、「やりたいこと」や「過去の経験」にフォーカスしすぎて、「価値観」や「働き方の相性」に関連するように分析できていないケースが多いです。
本当に納得できる企業選びのために必要な2つのこと
1. 自分の価値観を言語化すること 「楽しかった」「やりがいがあった」で終わらせず、「なぜそう感じたのか?」まで掘り下げる。そこから見えた価値観が企業選びに生きてくるのです。
2.言語化した価値観を抽象化すること 過去を深堀っただけでは企業選びにはいかせません。自分の価値観を一般化することで、企業選びに応用することができます。
2. 企業を「自分軸」で見る視点を持つこと
企業の知名度や年収だけでなく、「自分の価値観と合うか?」「自分が力を発揮できる環境か?」という視点で企業を評価する。
最後に
私自身、最初は「有名な企業に入れればいいや」と思っていました。でも自己分析を通じて「チームで目標に向かって努力して目標達成することに価値を感じる」という価値観が分かってからは、企業選びがスッキリしました。
やり方を少し変えるだけで、企業選びのモヤモヤが一気にクリアになります。あなたも自分に合った企業に出会えることを心から願っています。
「でも、本当に自分に合う企業が見つかるか不安…」という方、大丈夫です。もちろん完璧な企業はありません。
ですが、価値観が合う企業なら必ず見つかります。焦らず、じっくり向き合ってみてくださいね。

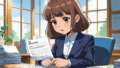
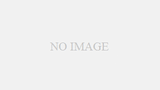
コメント