日産・ホンダの事情をわかりやすく解説!
日産・ホンダの経営統合が破談となったことがニュースにあり、世間を騒がせています。
このニュースからわかることは
もう大手企業=安定じゃないよっ!!
ということです。
就活生は特にですが、世の中で「大手企業」のくくりで見てはいけないと言われている中でも「大手思考」の方はまだまだたくさんいると実感しています。
「大手だしみんな名前知ってるし」というステータスが欲しいがために入った企業が次の年には経営破綻、倒産寸前、、なんてこともあり得るわけです。
そこで今日は
・日産ホンダの「経営統合破談」の実態をわかりやすく解説
・その事実を受けてどうやって会社を見極めていけばいいの?
という観点からお話ししたいと思います!
日産・ホンダ「経営統合の撤回」事情とは?
2025年2月13日日産とホンダが「経営統合の撤回」を正式に発表しました。
この二つの大手企業も実際はもう1つの会社では生きていけないと言われています。
流れとしてはこんな感じです。
日産・ホンダ:
持ち株はお互いに共同で経営統合しましょう!
ホンダ:
日産と経営統合する話をしたら、経営陣や株主が反発してきたよ、株価も下落 してしまった。
(ホンダは日産側はリストラ案の進捗が遅れていることも不信感がありました。)
ホンダ:
日産との共同持ち株のままでは経営がうまくいかないから、
日産の株をすべてホンダのものにして子会社化し、うちの傘下に入ってもらおう!
日産:
ちょっとまったー!当初の話と違う!子会社にはなれません!
こんな感じでお互いに条件に納得できない状況が相次いで経営統合が破談となったわけです。
なんでそもそも経営統合に至ったのか、日産ホンダは今後どのように対策していくのか、解説していきます。
日産がホンダと提携しなくてはならなかった理由=経営難
日産の経営の低下は2024年から顕著に現れました。
理由は外国市場での経営方針の甘さによる経営難です。
日産の販売台数の6割は外国市場であり、
中国が2割、アメリカがなんと4割も占めています。
特にアメリカに対する戦略ミスの打撃は大きかったそうです。
コロナ以降、電気自動車(EV)を売り出していましたが、急激にハイブリット車の需要が高まった状況にうまく対応できなかったのです。
そこで日産は強行突破「インセンティブ(販売奨励金)」の策を出します。
このインセンティブとは、「店舗の車の販売促進してね」とお願いするために払うお金のことです。
しかし、これも経営の改善にはならず、アメリカも不信感を抱き、次いで中国もその影響で不信感を抱き、利益が急激に下がっていきました。
どのぐらい下がったかというと、
前年度から売り上げは90.2%減の329億円
7月には通期営業利益の見通しを5000億円から1500億円と、金額を下げる形で修正しました。
こうなったら1社ではもう生き残れません。
ホンダと経営統合して協働でやることで会社を存続させなければ!
このような考えになったわけです。
ホンダが日産と提携しようとした理由
ホンダは日産ほど利益が下落しているわけではありませんでした。
しかし、2019年の世界販売台数は518万台、2024年といえば381万台であり、
5年で販売台数は150万台も減っているという状況です。
まだ財政地盤が固い今のうちに立て直しを図っています。
その立て直しのため、日産と提携しようとしたのです。
今後の両社の動向とは?
日産は新たな経営施策として
・タイ工場など3工場を閉鎖し、4000億の固定費などを削減
また、台湾の「ホンハイ精密工業」が日産との提供を狙っていると話題になっています。
しかし、外資系の企業であるため「日本の車は宝であり、その技術が外国に流出するのが怖い」などの不安の声も上がっています。
一方で、ホンダの今後の動向はどうなっていくのでしょうか。
日産との経営統合が破談となった今、新たに提携する会社を探していかなければ、経営の立て直しは難しいでしょう。
これに対しては「日産と組むくらいなら世界的にM&Aをすべきだ」「ホンダの独自の道を進んでほしい」など様々な意見が飛び交っています。
大手企業=安定ではない!企業をどう見極める?
今までの話でブランドだけでは安定している会社だと言えないことがわかります。
じゃあどうやって見極めればいいの?どうやって今後を考えたらいいの?
と不安になると思います。
就活時にやるべきことを主に三つ紹介します。
会社比較の徹底をする
今回の例でいうと日産・ホンダ・トヨタの三大自動車企業を比較して、
・どのような経営戦略を立てているのか(IR計画など)
・今までの収益の動向
などを比較すると、日産は今電気自動車を売り出しているんだなどと、まず、企業にまつわるニュースの情報を得ることが会社を知る第一歩に繋がります。
社員訪問を徹底する
これは特に大切で、先ほどの会社比較した知識を持ったうえで、社員訪問することで、
社員の方が考えている会社の強みはもちろん、弱みが見えてきます。
私も実際社員訪問することで「まずこの業界の課題は〇〇だな、それに対してこの企業は対策ができていない、他者と比べて考えが弱いな」と思えたことがあります。
社員訪問では本気で社員さんも向き合って話してくれる方が多いのでぜひたくさん活用してみてください。
転職を見据えて企業を考える
もう日本の企業の終身雇用の時代は終わっています。日本最大級と言われているトヨタ自動車ですら、「終身雇用を前提とした雇用はもうできない」と言っています。
そこで就活生が考えるべきは、

この企業に行って、次にどういうキャリアプランが描けるんだろう?
ということです。
コンサル、IT、人材、不動産、航空、メーカーなど様々な業界がありますが、
どの業界でも生きてくる知識が得られるのか、
はたまたその業界のみで通用する知識なのか
その業界の需要は伸びている傾向にあるか
はたまたその業界は需要が下がっているのか
これによってキャリアの幅は変わってきます。

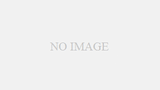

コメント